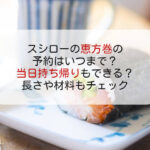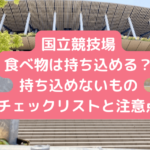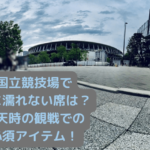2025年の大阪・関西万博の開催地「夢洲(ゆめしま)」。
たくさんの人が注目の人工島は、万博終了後にどんな姿へと変わるのか?
「イベントが終わったら、跡地はどうなるの?」そんな疑問を持つ人も多いでしょう。
実は、夢洲ではすでに複数段階の再開発計画が進行中。
統合型リゾート(IR)からエンタメ施設、長期滞在型リゾートまで――
“万博のその先”を見据えた壮大なプロジェクトが始まっています。
こちらでは、夢洲跡地の開発予定や候補地の最新情報、そして一般利用がいつから可能になるのかまで、分かりやすく紹介します。
夢洲がどのような未来を迎えるのか、今から期待が高まりますね!
大阪万博の跡地、何になる?どんな未来が待ってるの?

夢洲(ゆめしま)で開催される大阪万博2025の跡地は、なんと約155ヘクタールという広大な面積を誇ります。
比較のために言うと、東京ディズニーランドの敷地面積は約51ヘクタールなので、夢洲の跡地はその約3倍の広さ!
大阪万博2025の開催地「夢洲(ゆめしま)」は、万博終了後も“終わり”ではありません。
むしろ、ここからが本当の始まり。
跡地は今後、国際観光拠点や統合型リゾート(IR)などが集結する、新しい都市空間として生まれ変わろうとしています。
現在、「夢洲第2期区域」と呼ばれる約50ヘクタールもの広大なエリアで、本格的な開発計画が進行中。
大阪市と大阪府は「夢洲第2期区域マスタープラン」を策定し、まちづくりの方向性を明確にしながら、民間事業者を公募する二段階募集を行っています。
この夢洲の未来を担う企業の提案の中には、エンタメ、ビジネス、医療、研究、リゾートなど、多彩な構想が並びました。
たとえば、サーキット場やウォーターパーク、劇場、複合リゾート施設、ラグジュアリーホテルといった開発案が優秀提案として選ばれています。
つまり、夢洲は「万博の跡地」というだけでなく、大阪を代表する国際観光都市の新拠点へと進化していくのです。
なかでも注目されているのが、北側に位置する「IR連携ゾーン」。
ここには、カジノを含む統合型リゾート(IR)をはじめ、国際会議場やホテル、MICE施設(ビジネスイベント拠点)などが整備され、2030年秋ごろの開業を目指しています。
世界中の観光客が訪れ、ビジネス・娯楽・宿泊がすべて楽しめる“次世代の観光エリア”として期待が高まっています。
さらに、「健康・医療ゾーン」では、万博で展示されたヘルスケアパビリオンの理念を引き継ぎ、先端医療やライフサイエンス関連施設の導入も検討中。
研究者や企業が集まり、健康・長寿社会の発信拠点としての役割を担う可能性があります。
一方で、エンターテインメント分野でもワクワクする構想が進んでいます。
一部区画にはサーキット場やウォーターパーク、劇場、商業モールなど、子どもから大人まで楽しめる施設群の開発案が登場。
加えて、高級感あふれるラグジュアリーホテルの建設も予定されており、「泊まる・遊ぶ・働く・癒やす」がすべて叶うエリアになることが期待されています。
また、万博のレガシーとして注目されているのが、「大屋根リング」や「静けさの森」など、象徴的な施設の一部保存計画です。
“未来社会の実験場”としての記憶を残しながら、次の世代へとつなぐ都市空間づくりが進められています。
今後のスケジュールとしては、2025年の万博閉幕後、パビリオンなどの撤去作業が2027年度中に完了する予定。
その後、段階的に本格的な開発がスタート。
2030年ごろには、夢洲の新たな姿が徐々に形になっていく見込みです。
中には、「USJやディズニーランドのような大規模テーマパークとの連携」を求める声もあり、商工会議所などでも議論が続いています。
ただし現時点では、IRを中心とした国際観光・エンタメ都市構想が最有力とされています。
大阪万博跡地・夢洲は、日本初の“都市再開発型万博跡地”として、観光・ビジネス・医療・エンタメを融合させた未来型都市へと進化する場所。
2030年以降も段階的な拡張が計画されており、大阪の新しいランドマーク誕生まで、期待は高まる一方!
大阪万博跡地(夢洲第2期区域)の詳細!

大阪万博2025の跡地「夢洲第2期区域」は、2030年代に向けた本格開発の目玉ゾーンとして注目を集めています。
特に優秀提案として選ばれたのは、国際水準のモータースポーツサーキットと世界クラスのウォーターパーク。
どちらも大阪IRと連携し、夢洲全体の経済波及や都市魅力度向上を目指した複合エンターテインメント都市の形成が狙いです。
サーキットの詳細:OSAKA CIRCUIT(仮称)
大林組グループの提案によるサーキット「OSAKA CIRCUIT(仮称)」は、将来的にF1など国際モータースポーツ大会の誘致を視野に入れた本格拠点。
単なるサーキットだけでなく、周辺には車をテーマにしたアミューズメントパーク、会員制ヴィラ、高級ホテル、大型アリーナ、ショッピングモールなども併設される予定です。
このサーキットは、都市型複合エンタメ拠点の核として設計されており、MICE(国際会議・展示場)機能やアート展示、自然空間「静けさの森」の再整備も盛り込まれています。
つまり、観光・レジャー・文化・ビジネスを一体化した、夢洲の新しいランドマークとなる都市型エンタメ空間になるわけです。
ウォーターパークの詳細:世界クラスの水の楽園
一方、関電不動産開発グループの提案では、スライダーや多彩なアトラクションを備えた世界クラスのウォーターパークが核として計画されています。
ここにはラグジュアリーホテル、商業施設、劇場街、ライブエンタメゾーンが一体化され、都市型エンタメリゾートとして整備される予定です。
ウォーターパークは、ファミリー層やインバウンド観光客向けの大規模リゾート施設として位置づけられ、都市らしい賑わいゾーンと緑地・公園空間の融合も図られています。
利便性と非日常性の両立がテーマで、日帰りでも宿泊でも楽しめる構造です。
万博跡地の象徴的な場所との連携
これらの施設開発計画には、万博の象徴施設である「大屋根リング」や「静けさの森」の保存・再利用も含まれており、過去の万博レガシーを未来都市に融合させる狙いがあります。
現時点では具体的な施設規模や開業時期は未確定ですが、いずれも2030年代の本格開発とIRとの連動を想定しており、国内外からの集客効果や経済波及への期待は大きいです。
夢洲第2期区域は、モータースポーツの興奮と水上リゾートの楽しさが同じエリアで体験できる、まさに“複合都市型リゾート”。
2030年代には、大阪万博跡地としてだけでなく、国際観光・エンタメの最前線を体感できる未来都市として世界の注目を集めるはず。
万博跡地の施設開業はいつになる?スケジュールや規模!
大阪万博2025の跡地「夢洲(ゆめしま)」では、2030年秋ごろの開業を目指して、日本初となる本格的な統合型リゾート(IR)の建設が進められています。
万博の興奮が冷めやらぬうちに、今度は世界から観光客を呼び込む一大プロジェクトがスタートします。
開業スケジュールは?
IRの建設工事は、2025年春に本格着工。
すでに2025年4月には起工式が行われ、現地では準備が着々と進行中です。
今後の予定としては、2030年夏に建設工事が完了し、同年秋ごろの正式開業を目標としています。
万博閉幕(2025年10月)から約5年後、夢洲は「万博の跡地」から「国際リゾート都市」へと華麗に転身することになります。
このIR整備と並行して、周辺の第2期区域(約50ヘクタール)でも都市観光・商業・エンタメ施設などの開発が進められ、夢洲全体が大阪の新しい観光ハブとして生まれ変わります。
施設の規模は?巨大リゾートの広さ
IRが建設されるのは、夢洲北側の約49ヘクタール(東京ドーム約10個分)におよぶエリア。
まさに“ひとつの都市”が新たに誕生するほどのスケールです。
その中核となるのはもちろんカジノ施設。
ただし、全体の敷地面積のうちカジノ部分は3%未満に抑えられています。
むしろ主軸は、宿泊・商業・国際会議・エンタメなど多面的な施設構成にあります。
IRの中心には、総客室数約2,500室を誇る高級ホテル群や、6,000人以上を収容できる国際会議場(MICE施設)、大規模展示場、エンターテインメント施設、そして大型ショッピングモールが整備される予定です。
つまり、カジノに依存しない「滞在型・複合型リゾート」を目指しているのが大阪IRの最大の特徴。
観光だけでなく、国際的なビジネス会議や展示イベントの開催も見据え、世界水準の都市機能を備えます。
経済効果と来訪者数の想定!
大阪IRの想定年間来訪者数は、なんと約2,000万人(国内1,400万人+海外600万人)。
この規模はUSJをも上回るともいわれており、大阪観光の新しい起爆剤として大きな期待が寄せられています。
経済波及効果は年間約1兆1,400億円、そして9万人以上の雇用創出が見込まれています。
単なる観光地ではなく、地域経済を支える産業拠点としての役割も!
夢洲が描く未来は日本初の“海上リゾート都市”!
IRは、万博跡地の中でも特にシンボリックな存在となりそう。
2030年の開業を皮切りに、夢洲では次々と新しい施設や都市機能が整備され、日本初の“海上リゾート都市”として世界中の注目を集めるはずです。
「万博の舞台だった夢洲が、今度は世界をもてなすステージへ」――。
大阪の未来を大きく変えるこの一大プロジェクトから、目が離せません!
大阪万博の大屋根リングはどうなる?
大阪万博2025の象徴的存在といえば、やはり「大屋根リング」ですよね。
会場の中央をぐるりと囲むように配置された、全長約2kmにも及ぶ巨大な木造構造物は、世界的にも注目を集めています。
のスケール感とデザインは、まさに「未来社会の象徴」としてふさわしいものでした。
ですが、気になるのは万博閉幕後、この大屋根リングがどうなるのか?ということ。
実は、すべてをそのまま残すわけではなく、一部(北東側約200メートル)が現状に近い形で保存される方針が決まっています!
一部保存と公園化の方針が決まってる!
大阪市は、リングの保存部分を中心に「都市公園」として再整備する計画を進めています。
保存される約200メートルの区間は、人が上れる展望回廊として整備される予定で、一般市民が自由に訪れられる憩いの場に。
つまり、万博会期中のように“特別な入場券がないと入れない空間”ではなく、誰でも気軽に万博の記憶を感じられる場所へと生まれ変わるのです。
リング周辺の約3.3ヘクタールの敷地もあわせて都市公園として整備される予定で、緑に囲まれたオープンスペースになる構想です。
コストと現実的な選択
大屋根リングをすべて残すには莫大な費用がかかるため、「部分保存+リユース」という現実的な選択がなされました。
保存部分を「準用工作物」として扱えば、防火や耐火などの改修コストを抑えられ、約41億円で保存可能と試算されています。
一方、飲食店や商業スペースなど事業性を持たせた“建築物”として残す場合は最大76億円が必要になるとのこと。
さらに、維持管理費として10年間で約16億円が見込まれています。
市はこれらの費用を余剰金・補助金・寄付金などを組み合わせてまかなう方針を示しており、財政面で無理のない運営を目指しているようです!
市民の声は?
もちろん、市民の中には「全体を残してほしい!」という声も少なくありません。
署名活動なども行われましたが、維持費・耐久性・安全性などの課題から、最終的には部分保存とリユース案で落ち着きました。
とはいえ、解体される部分もただ捨てられるわけではなく、ベンチや休憩施設の素材として再利用(リユース)される計画も進行中。
こうした発想は、まさに“サステナブル(持続可能)な社会”という万博テーマの体現とも言えそう!
万博を未来へ残す意味!
残される北東側のリングは、夢洲を代表する新たなランドマークとして、市民や観光客の憩いの場となるはず!
高い場所から大阪湾を一望できる展望回廊は、きっと多くの人が訪れるフォトスポットになりそうです。
そして何より、この構造物は日本の木造建築技術の粋を集めたシンボル。
その一部が後世に残ることは、“万博の記憶”と“木の文化”を未来へつなぐ大切な役割を果たすことになります。
つまり、大屋根リングの保存は完全な終わりではなく、新たな始まりの象徴。
万博の熱気を静かに受け継ぎながら、人々が集い、思い出を語り合う場所として夢洲に残っていくことに♪
他の万博跡地ってどうなった?過去事例から見る“成功と失敗”
万博跡地は、未来都市や観光拠点としての可能性を秘めていますが、過去の事例を振り返ると成功と失敗がはっきり分かれることがわかります。
大阪万博1970(EXPO’70)跡地の例
1970年に開催された大阪万博の跡地は、「万博記念公園」として約258ヘクタールの広大な緑地・文化空間に生まれ変わりました。
ここには太陽の塔、日本庭園、国立民族学博物館など、万博のシンボル施設が点在しており、閉会後も活用されています。
さらに、自然文化園、スポーツ・レクリエーション施設、レジャーゾーン「EXPOCITY」など、新しい施設も随時整備され、時代に合わせて進化。
その結果、来園者数は安定し、関西有数の都市型文化公園として現代まで人気を維持。
成功の背景にはいくつかのポイントがあります。
まず、シンボル施設の保存と自然・文化的空間の両立。
次に、都市近郊の好立地と、鉄道・高速道路など交通インフラとの連携。
そして、EXPOCITYのような新施設の増設による継続的な魅力の更新です。
こうした要素が揃ったことで、1970年の跡地は世界的にも成功事例として評価されています。
■ 海外の万博跡地:成功と失敗の両例
海外でも万博跡地の活用には明暗があるようです・・。
- モントリオール1967年
パークや博物館群を整備しましたが、財政問題や施設維持費の高騰が課題に。部分的成功に留まります。 - セビリア1992年
住宅地や会議場に転用されましたが、老朽化や商業施設の空きが目立ち、失敗事例とされています。 - 上海2010年
万博文化公園や記念ホールを整備し観光名所化に成功。官民連携による再活性化が鍵でした。 - シドニー2000五輪跡地(参考)
商業・住宅地に完全再利用され、民間主導で賑わいが創出されました。成功例です。
失敗例には、用途が不明確、経営主体が頻繁に変わる、再投資が進まないという共通点があります。
一方、成功例はシンボル施設の継続的保存、複合機能化、定期イベントやインバウンド集客策がポイント。
過去事例から学ぶ万博跡地活用のポイントとは?
大阪万博1970の跡地は、公園化+文化・レジャー複合の路線が功を奏し、世代を超えて楽しめる都市型空間として定着しました。
海外でも、上海やシドニーのように官民連携で跡地を再活性化し、都市機能と観光資源に結びつける取り組みが成功しやすい傾向があります。
つまり、万博跡地を単なる観光施設や展示会場で終わらせず、文化・商業・自然・住環境を融合させた複合都市として設計することが、長期的な成功のカギとなりそう!
大阪万博2025の夢洲も、こうした過去の成功・失敗事例を参考に、未来都市としてどう魅力を維持するかが問われています!
他の記事もチェック
まとめ
大阪万博2025の跡地は、単に空き地となるのではなく、夢洲の壮大な開発プロジェクトとして未来へと引き継がれていきます。
エンターテインメントやリゾート、さらには健康志向の施設まで、多彩な利用計画が進行中です。
万博終了後も、夢洲がどのように進化していくのか、私たちはその変貌を楽しみに見守りたいですね。